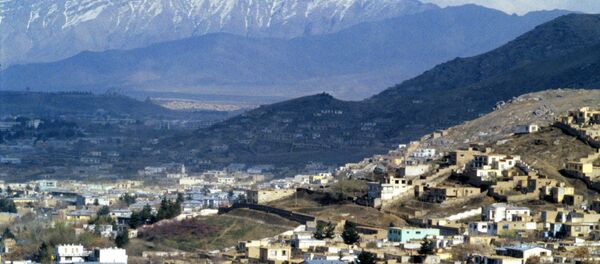スプートニク日本
軍事サービス市場の拡大傾向について、またこうした傾向に潜む可能性のある躓きの石について、戦略動向センターの専門家、ウラジーミル・ネヨロフ氏はスプートニクからの取材に対し、次のように語っている。
ネヨロフ氏:「確かにロシア内外のプレスはこの450社という数値をよく引いている。とはいえ、最初にこの数値を挙げたのがどこなのかもはっきりしていない。民間軍事会社の数を正確に把握するのはこれをカウントする統一したシステムのない以上、非常に困難だ。理由はこうした商業的なストラクチャーが国際法的の中で未だに位置づけが確定していないことに関係しているが、この問題は国際連合をはじめとする国際組織レベルではすでに何年も議論の対象になっている。国際舞台での民間軍事会社の活動を多少なりとも規定しようとして、2008年9月、スイスのモントルーで17か国によって、いわゆる『モントルー文書』が批准された。この文書は紛争地帯で活動する民間軍事、警備会社に関するもので、こうした企業の組織と機能の一定の原則体系を作ることを目的とした、一種、その行動を定めた法典といえる。法典が順守されているかを管理するメカニズムとして機能しているのは国際法協会となっている。同協会は定期的に文書に署名している会社リストを公表しているが、それでもモントルー文書は法的拘束力を持たず、本質的には新たな国際法規を作るものでもない。こうしたことから民間軍事会社は国際法体系の視点からするとグレーゾーンにとどまり続けている。」
ネヨロフ氏:「これにどう対応しようと、今すでにある傾向を無視するというのは、少なくとも近視眼的だ。軍事分野での国家の機能を民間軍事会社に完全に委任することはもちろんできない。こうした場合、制御不能に陥ってしまいかねないからだ。こうした商業的ストラクチャーはVIPの警護、船舶、貨物の随伴、後方支援、地雷解除、軍事通訳、人材育成など、たくさんの種類の活動に用いることが可能だ。」