「消したいあの一年」
原爆投下から75年
スプートニク特派員の広島取材
スプートニク特派員の広島取材

2020年は広島と長崎への原爆投下から75年目にあたる。原爆投下の日を前に、通信社スプートニクの特派員が1945年8月6日午前8時15分に原子爆弾が投下され、わずか10秒の間に地表からほぼすべてが消え去ってしまった広島を訪れた。
高齢化する被爆者
広島訪問は私の不安を掻き立てた。それはこの町が恐ろしい悲劇を今も覚えているからだけでない。
現在、被爆者の平均年齢は84歳。日本全国の被爆者は約13万人とされている。また共同通信のアンケートによると、被爆者の約25%が年齢や体力の影響で被爆体験の継承活動が減ってきているという。また約13%が活動をやめ、約40%が幼い頃に被爆したため記憶がないなどの理由で元々活動はしていなかったという。従来通り活動ができそうだという被爆者はわずか19%。
また新型コロナウイルスの流行が状況をさらに複雑にしている。共同通信のアンケートでは半数以上の回答者が、新型コロナウイルスが今後の核兵器廃絶運動の妨げとなると答えた。また年を追うごとに、核廃絶が将来実現することを信じる被爆者が少なくなっている。
被爆者が忘れ去られないようにするためには、どうしたらいいのだろうか?核兵器によるこの無慈悲な悪夢をもう誰も経験しなくてすむようにするためには、どうしたらいいのだろうか?そのような問いかけが広島訪問中、私の頭から離れなかった。そしてこの問いへの答えを、今回の取材で出会ったさまざまな人たちから得た。
被爆者が忘れ去られないようにするためには、どうしたらいいのだろうか?核兵器によるこの無慈悲な悪夢をもう誰も経験しなくてすむようにするためには、どうしたらいいのだろうか?そのような問いかけが広島訪問中、私の頭から離れなかった。そしてこの問いへの答えを、今回の取材で出会ったさまざまな人たちから得た。
1
滝川 卓男 「被爆の実相を100年後でも残す」
広島訪問で最初に訪れたのは広島平和記念資料館だった。そこでは2019年4月に館長に就任した滝川卓男氏(61)が外国人ジャーナリストたちのために1時間にわたり案内してくれた。滝川氏は、昨年完了した3回目の大規模改修後に資料館の展示物がどのように変化したのかを詳しく説明してくれた-
「本館の一番の目的は被爆の実相を世界に発信すると言うこと。これが私達の役割・使命です。そういったもとに実は10年間かけて大学の先生、それから被爆者、それから博物館関係の専門家、そういった方の議論を経て昨年リニューアルした展示の構成にしました。ですから、専門的に幅広く意見を聞いた上で今回のリニューアルができました。」
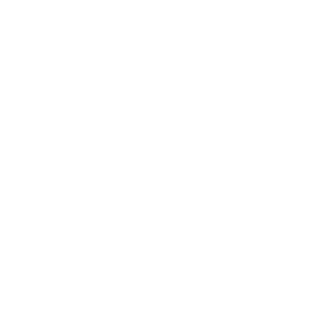
滝川卓男
館長
広島平和記念資料館のリニューアルは注目を集め、2019年の入館者数は176万人に達し、黒人初の米大統領に就任したバラク・オバマ氏が広島を公式訪問した2016年の記録(174万人)を更新した。
改修後、資料館の展示物には1945年の広島への原爆投下で亡くなった人たちのたくさんの写真や私物が加わった。また当時、広島市内にいて被爆した外国人に関するセクションもつくられた。滝川氏は、被爆の実相を伝えることを目的としたリニューアルについて、次のように説明した-
“
今回のリニューアルの大きなコンセプトは被爆者が高齢化していく中で被爆の実相を100年後でも残していこうというものです。そのためには一つは実物主義。そういうものを展示してくつもりです。実物は100年経っても本物ですよね。そういった考え方をもとに考えれば、前回展示されていた再現人形は作ったものです。ですから、作ったものは今回のリニューアルでは展示しないということになりました。
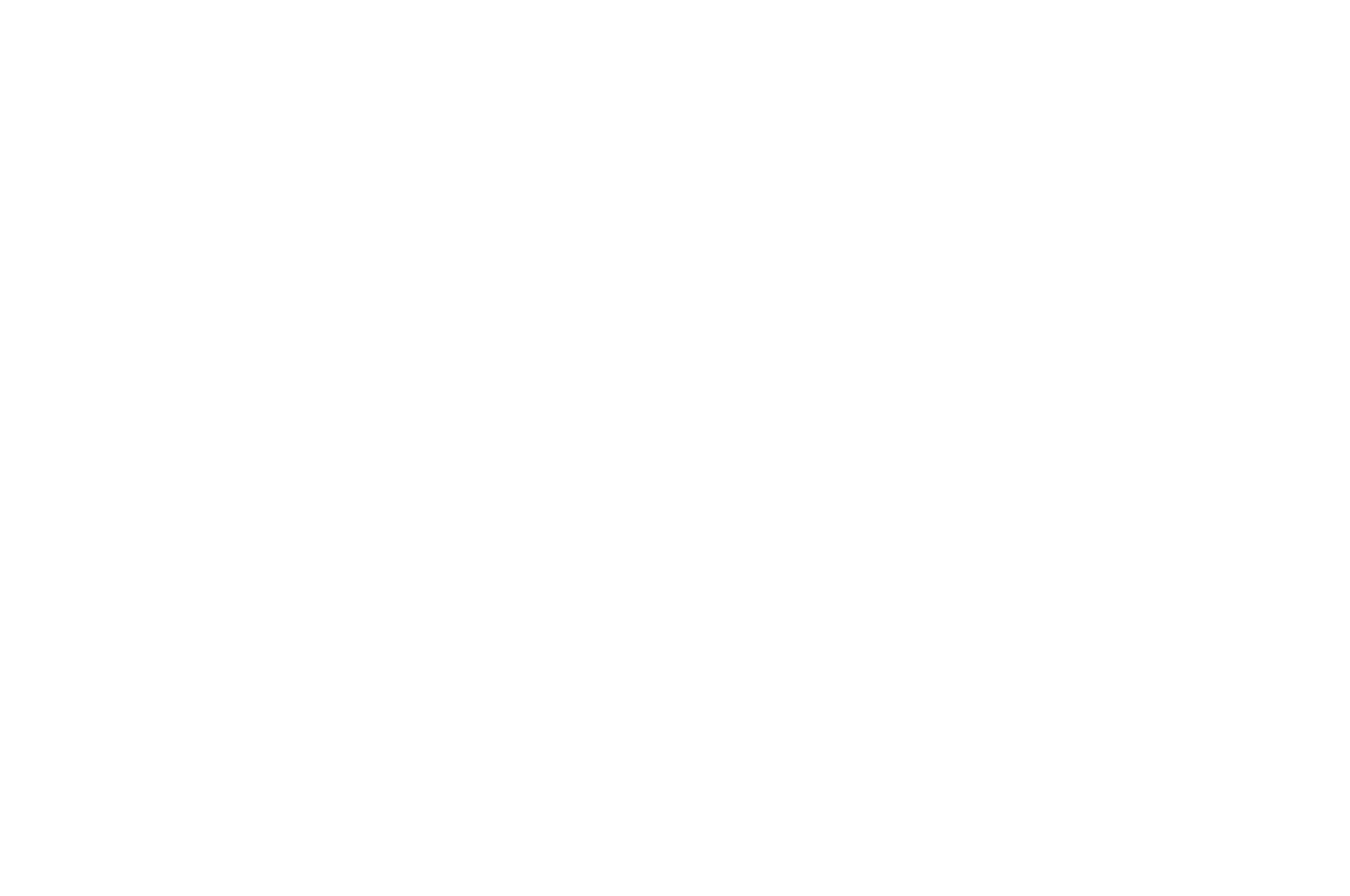
広島平和記念資料館は、「人影の石」や「伸ちゃんの三輪車」などの有名な展示物のほかに、被爆者が描いた5000点以上の絵も所蔵している。
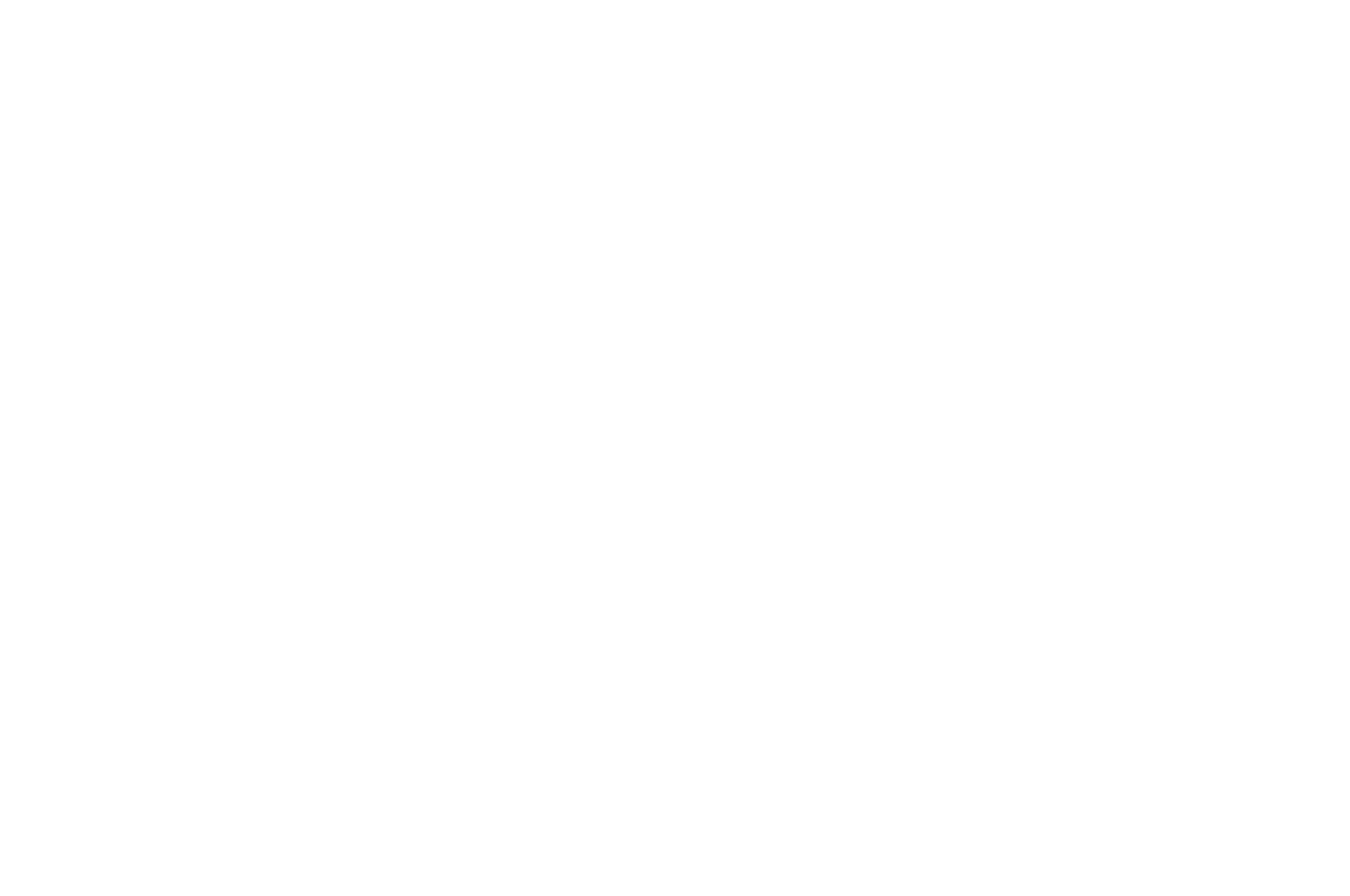
また滝川氏は、資料館に展示されている「黒い雨」の痕跡が残る壁について解説した際、嬉しいニュースを伝えた。7月29日、広島地方裁判所は、広島への原爆投下直後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたとして住民ら84人が広島市や県に対し被爆者健康手帳の交付などを訴えた裁判で、原告全員を被爆者と認める判決を言い渡した。
地元自体は、国が定める「黒い雨」の援護対象区域外の人たちも被爆者と認め、被爆者健康手帳を交付するよう繰り返し求めていたが、区域外にいた人たちの「黒い雨」による健康被害を裏付ける科学的根拠がないとして、政府は拒んできた。原告84人のうち9人は死亡しているが、被爆者と認定する判決はこの75年間で初となる真の成果となった。
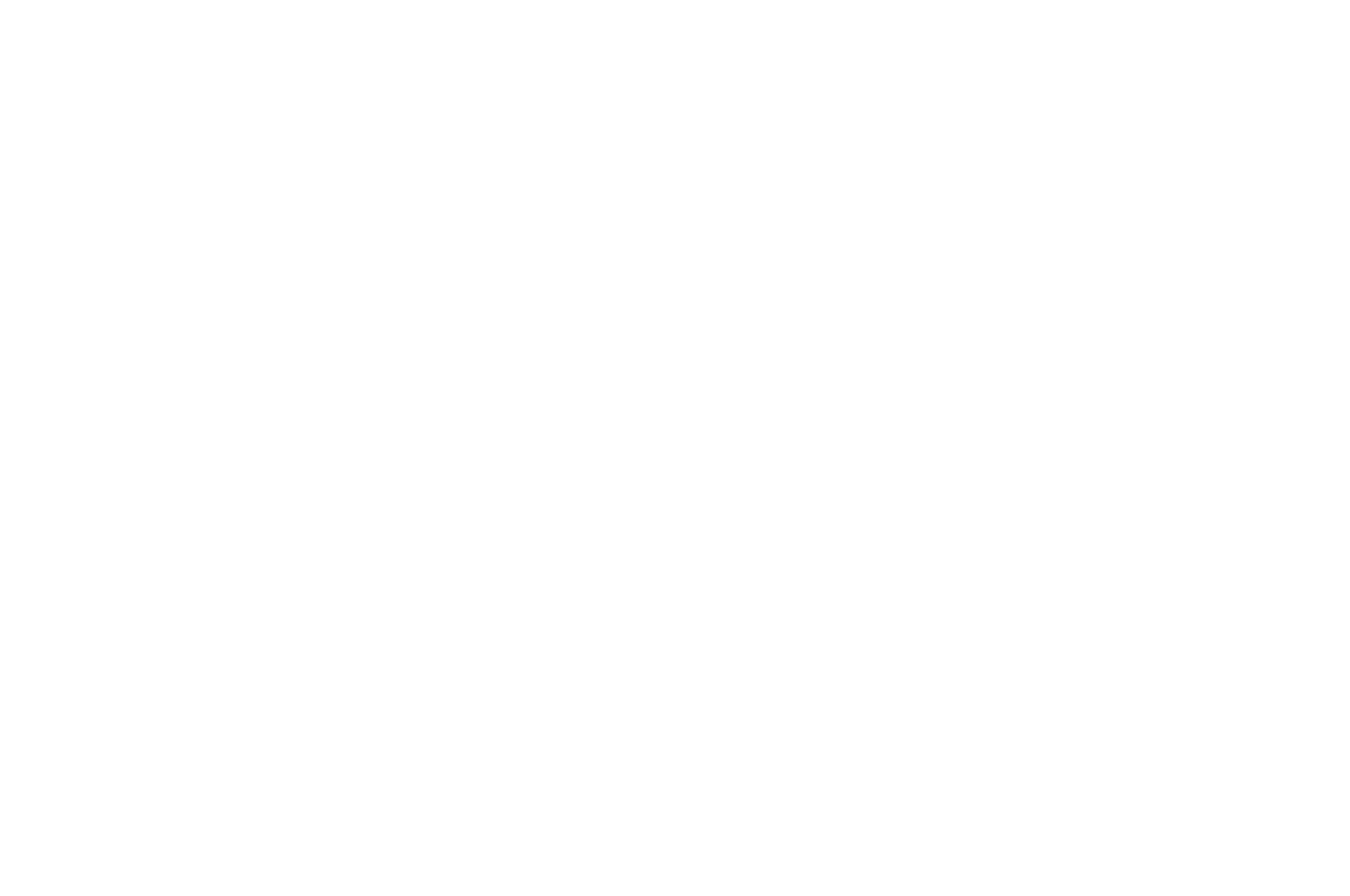
滝川氏は昨年、1つの目標を立てた。
それは被爆者の証言をできるだけたくさんビデオに収録することだ。2年間で約37人の被爆者の証言を収録する計画だった。しかし、新型コロナウイルスの影響で計画に変更が生じる可能性がある。
「コロナの影響は多少あると思います。でも、大きくずれることなく、やっていきたいと思っています。それにつけ加えて言うと、コロナの関係で3ヶ月休館していました。その間、60分で撮った講話をインターネットで流すようにしました。ですから、今回コロナで、インターネットを使って発信するということが大事だとわかりました。どんどん進めていったらいいという気持ちになりました。ですから収録にはちょっと証言者さんの体調とか、コロナの関係もありますので、多少遅れるかもしれませんけれど、全部やり切っていきます。」
「コロナの影響は多少あると思います。でも、大きくずれることなく、やっていきたいと思っています。それにつけ加えて言うと、コロナの関係で3ヶ月休館していました。その間、60分で撮った講話をインターネットで流すようにしました。ですから、今回コロナで、インターネットを使って発信するということが大事だとわかりました。どんどん進めていったらいいという気持ちになりました。ですから収録にはちょっと証言者さんの体調とか、コロナの関係もありますので、多少遅れるかもしれませんけれど、全部やり切っていきます。」
2
被爆者の寺本 貴司
「消したいあの一年」
「消したいあの一年」
滝川氏の案内で資料館を見学したあと、爆心地から1キロの自宅で被爆しながらも奇跡的に生き残った寺本貴司(85)氏と面会することができた。爆心地から1キロの生存率は50%とされており、当時、寺本氏の近くにいた多くの人は亡くなってしまったという。
生死のさかい
8月下旬ごろと思うが、朝起きると頭髪が抜けて、机にベッタリ着いた。身体中が痛くなり、毎日寝ていたが、離毛もひどく、まさに生死のさかいであった。「ピカにあった者は、頭の髪が抜けて、歯茎から出血したり、体に斑点が出て次々に死なれるそうだ。この子も助かれば良いが」との枕もとでの半睡状態の耳に入ってきた。私のことを話しているのかなと思いながらも、死の恐怖はなかったような覚えがある。
再度、小学校5年生
昭和21年4月、再度小学校5年生に入学し、当分の間は青空教室で学んだ。小学校5年生を2度繰り返しても、昭和20年の1年間が消えるものではない。母に心配をかけ、無惨な死に方をさせたとの思いなど、様々な思いが年を経るごとに大きくのしかかる50余年であった。戦争の愚かさや怒り、悲しみを多少とも伝え、核兵器の廃絶、恒久平和の実現に微々たりとも一助になればと、拙い文で恥ずかしくもあるが、記憶をたどり記した。
(寺本 貴司「消したいあの一年」『平和文化』第139号,2000年12月)
8月下旬ごろと思うが、朝起きると頭髪が抜けて、机にベッタリ着いた。身体中が痛くなり、毎日寝ていたが、離毛もひどく、まさに生死のさかいであった。「ピカにあった者は、頭の髪が抜けて、歯茎から出血したり、体に斑点が出て次々に死なれるそうだ。この子も助かれば良いが」との枕もとでの半睡状態の耳に入ってきた。私のことを話しているのかなと思いながらも、死の恐怖はなかったような覚えがある。
再度、小学校5年生
昭和21年4月、再度小学校5年生に入学し、当分の間は青空教室で学んだ。小学校5年生を2度繰り返しても、昭和20年の1年間が消えるものではない。母に心配をかけ、無惨な死に方をさせたとの思いなど、様々な思いが年を経るごとに大きくのしかかる50余年であった。戦争の愚かさや怒り、悲しみを多少とも伝え、核兵器の廃絶、恒久平和の実現に微々たりとも一助になればと、拙い文で恥ずかしくもあるが、記憶をたどり記した。
(寺本 貴司「消したいあの一年」『平和文化』第139号,2000年12月)
集団疎開から帰広
昭和20年当時私は10歳で、小学校5年生であった。集団疎開先で病気になり、8月4日に母が迎えに来た。当初8月6日に広島に帰る予定でいたが、1日でも早く帰りたく、母の疲れも考えず、その日のうちにすぐに帰り支度をした。
6日に帰れば、原爆に遭わずにいたものをと後悔が残る。
8月6日
朝7時半頃、半袖の下着とパンツだけの姿で外に出て、近所の友達3-4人と青空を見上げ、B29の話などして遊んでいると、母が「病院に行くから支度をしなさい」と呼びに来た。(8時頃と思う。)家に帰り、母は身支度、私は机に向かい疎開先に手紙を書いていた。
昭和20年当時私は10歳で、小学校5年生であった。集団疎開先で病気になり、8月4日に母が迎えに来た。当初8月6日に広島に帰る予定でいたが、1日でも早く帰りたく、母の疲れも考えず、その日のうちにすぐに帰り支度をした。
6日に帰れば、原爆に遭わずにいたものをと後悔が残る。
8月6日
朝7時半頃、半袖の下着とパンツだけの姿で外に出て、近所の友達3-4人と青空を見上げ、B29の話などして遊んでいると、母が「病院に行くから支度をしなさい」と呼びに来た。(8時頃と思う。)家に帰り、母は身支度、私は机に向かい疎開先に手紙を書いていた。
その時、裏庭の窓の辺りがピカっと光り、振り向いた瞬間真っ暗になり、何が起きたのか判らず、ただうずくまっていた。しばらくすると向こうの方がボーッと明るくなり、その向こうに歩いて行くと道に出た。近所のおばさんが居り、私が近づくと「あんたは誰」と声をかけられ、「貴司です」と答えると、「あ、貴司ちゃん、一緒に逃げよう、おぶってあげるから」と私をおぶってくれた。辺りを見回しても母の姿が見えない。私は「お母ちゃんが、お母ちゃんがいない」と泣き叫んだ。おばさんが「お母ちゃんがどこ」と聞いたので、「お母ちゃんは僕と一緒に家の中にいた」と、なおも泣き叫んだ。近所の人たちも集まりだし、「お母ちゃんは、誰かが助けに行っているから、貴司ちゃんは、早く逃げなさい」と言われたので、おばさんに背負われて近所の人たちと一緒に山手方面へ逃げた。
私は、頭、顔に傷を負い、血だらけで、誰だか判らなかったとのことであった。
逃げる途中、瓦礫の中から首から上だけが出て、眼をキョロキョロさせていた女性がいた。この人はどうなったのか。私がすぐに燃え広がったので、もう焼き死んだのではないかと、いまだにあの情景が目に浮かんで、忘れることができない。
私は、頭、顔に傷を負い、血だらけで、誰だか判らなかったとのことであった。
逃げる途中、瓦礫の中から首から上だけが出て、眼をキョロキョロさせていた女性がいた。この人はどうなったのか。私がすぐに燃え広がったので、もう焼き死んだのではないかと、いまだにあの情景が目に浮かんで、忘れることができない。
大芝町辺りであったが、広島へ救授に出た帰りのトラックに乗せてもらい、古市町嚶鳴小学校前の白壁の塀に囲まれたお寺にたどり着いた。中にはすでに多くの人が居り、私たちは本堂入口の階段に腰かけて休んだ。
そこで、今朝一緒に遊んでいたK君と会った。私が帰宅した後も戸外にいたのか、大火傷を負い、両手を前にして歩いていた。前にした両手からはボロ布れのようなものが垂れ下がっており、よく見ると剥けた皮だった。彼は、2、3日後に死亡したと数日後に聞いた。
夕暮れ頃、父が尋ねてきた。「お母ちゃんは横川橋のふもとに居る」と聞き、少し安心した。
広島のほうの空は、赤く染まり、燃え上がるように見えた。夜遅くまでガラガラと荷車の通る音が聞こえ、川原で物を燃やす火が見えた。
7日朝私は、怪我人で満員の汽車とバスを乗り継ぎ、山県郡の叔母の所へ行き、療養させてもらうことになった。
そこで、今朝一緒に遊んでいたK君と会った。私が帰宅した後も戸外にいたのか、大火傷を負い、両手を前にして歩いていた。前にした両手からはボロ布れのようなものが垂れ下がっており、よく見ると剥けた皮だった。彼は、2、3日後に死亡したと数日後に聞いた。
夕暮れ頃、父が尋ねてきた。「お母ちゃんは横川橋のふもとに居る」と聞き、少し安心した。
広島のほうの空は、赤く染まり、燃え上がるように見えた。夜遅くまでガラガラと荷車の通る音が聞こえ、川原で物を燃やす火が見えた。
7日朝私は、怪我人で満員の汽車とバスを乗り継ぎ、山県郡の叔母の所へ行き、療養させてもらうことになった。
母の死
15日、敗戦の放送を聞いた翌日であったか、もうすぐ姉と一緒に母が来ると聞き、待っていると姉だけの姿が見えた。「お母ちゃんは」と聞くと、小さな箱を示し、「ここに居る」と言っただけだった。
何年か後、姉から母の様子を聞くことができた。母は家の下敷きになっていたところを助け出され、横川橋のふもとまで連れて逃げてもらったが、歩けなくなったので、川土手の臨時収容所で寝ていた。日々衰弱がひどくなり、8月15日夕刻に死亡した。遺体も7-8人並べて一度に火葬する状態で、母の遺体を置いた場所の遺骨を少し持って帰ったとのことであった。
私を背負ってくださったおばさんや、古市まで一緒に逃げた近所の人たちの多くが、2-3ヶ月の内に死なれたと聞いた。
15日、敗戦の放送を聞いた翌日であったか、もうすぐ姉と一緒に母が来ると聞き、待っていると姉だけの姿が見えた。「お母ちゃんは」と聞くと、小さな箱を示し、「ここに居る」と言っただけだった。
何年か後、姉から母の様子を聞くことができた。母は家の下敷きになっていたところを助け出され、横川橋のふもとまで連れて逃げてもらったが、歩けなくなったので、川土手の臨時収容所で寝ていた。日々衰弱がひどくなり、8月15日夕刻に死亡した。遺体も7-8人並べて一度に火葬する状態で、母の遺体を置いた場所の遺骨を少し持って帰ったとのことであった。
私を背負ってくださったおばさんや、古市まで一緒に逃げた近所の人たちの多くが、2-3ヶ月の内に死なれたと聞いた。
生死のさかい
8月下旬ごろと思うが、朝起きると頭髪が抜けて、机にベッタリ着いた。身体中が痛くなり、毎日寝ていたが、離毛もひどく、まさに生死のさかいであった。「ピカにあった者は、頭の髪が抜けて、歯茎から出血したり、体に斑点が出て次々に死なれるそうだ。この子も助かれば良いが」との枕もとでの半睡状態の耳に入ってきた。私のことを話しているのかなと思いながらも、死の恐怖はなかったような覚えがある。
再度、小学校5年生
昭和21年4月、再度小学校5年生に入学し、当分の間は青空教室で学んだ。小学校5年生を2度繰り返しても、昭和20年の1年間が消えるものではない。母に心配をかけ、無惨な死に方をさせたとの思いなど、様々な思いが年を経るごとに大きくのしかかる50余年であった。戦争の愚かさや怒り、悲しみを多少とも伝え、核兵器の廃絶、恒久平和の実現に微々たりとも一助になればと、拙い文で恥ずかしくもあるが、記憶をたどり記した。
(寺本 貴司「消したいあの一年」『平和文化』第139号,2000年12月)
8月下旬ごろと思うが、朝起きると頭髪が抜けて、机にベッタリ着いた。身体中が痛くなり、毎日寝ていたが、離毛もひどく、まさに生死のさかいであった。「ピカにあった者は、頭の髪が抜けて、歯茎から出血したり、体に斑点が出て次々に死なれるそうだ。この子も助かれば良いが」との枕もとでの半睡状態の耳に入ってきた。私のことを話しているのかなと思いながらも、死の恐怖はなかったような覚えがある。
再度、小学校5年生
昭和21年4月、再度小学校5年生に入学し、当分の間は青空教室で学んだ。小学校5年生を2度繰り返しても、昭和20年の1年間が消えるものではない。母に心配をかけ、無惨な死に方をさせたとの思いなど、様々な思いが年を経るごとに大きくのしかかる50余年であった。戦争の愚かさや怒り、悲しみを多少とも伝え、核兵器の廃絶、恒久平和の実現に微々たりとも一助になればと、拙い文で恥ずかしくもあるが、記憶をたどり記した。
(寺本 貴司「消したいあの一年」『平和文化』第139号,2000年12月)
集団疎開から帰広
昭和20年当時私は10歳で、小学校5年生であった。集団疎開先で病気になり、8月4日に母が迎えに来た。当初8月6日に広島に帰る予定でいたが、1日でも早く帰りたく、母の疲れも考えず、その日のうちにすぐに帰り支度をした。
6日に帰れば、原爆に遭わずにいたものをと後悔が残る。
8月6日
朝7時半頃、半袖の下着とパンツだけの姿で外に出て、近所の友達3-4人と青空を見上げ、B29の話などして遊んでいると、母が「病院に行くから支度をしなさい」と呼びに来た。(8時頃と思う。)家に帰り、母は身支度、私は机に向かい疎開先に手紙を書いていた。
昭和20年当時私は10歳で、小学校5年生であった。集団疎開先で病気になり、8月4日に母が迎えに来た。当初8月6日に広島に帰る予定でいたが、1日でも早く帰りたく、母の疲れも考えず、その日のうちにすぐに帰り支度をした。
6日に帰れば、原爆に遭わずにいたものをと後悔が残る。
8月6日
朝7時半頃、半袖の下着とパンツだけの姿で外に出て、近所の友達3-4人と青空を見上げ、B29の話などして遊んでいると、母が「病院に行くから支度をしなさい」と呼びに来た。(8時頃と思う。)家に帰り、母は身支度、私は机に向かい疎開先に手紙を書いていた。
このような悲劇の後、どうしたら許したり、これから生きていく力を見つけることができるのだろうか?おそらくこれは被爆者に投げかけられる最も一般的な質問であろう。寺本氏は次のように答えた-
「『あんたは米国を憎むか』というような表現で質問されます。私の母が殺され、一緒に遊んでいた友達も殺されました。原爆で殺されたという思いからすれば、『憎くありません』というようなことは私には言えません。確かに憎いと思いました。しかし年をとるにつれて、私にも子どもができ、孫もでき、憎しみとか恨みとかそういうものはありません。私が言いたいのは、二度とこんなことがあってはならない、こういう残酷な事態が起きてはならないということです。これが私の願いです。当初から、このようなことがあってはらないと思っていたわけではありませんが、やはり年月が経つにつれて、自分の思いが変わってくるということがあります。このように皆さんに体験を話すのは、相手に憎しみを持っているのではない、こういう事実があったことを忘れてはいけない、こういうことが二度と起こらないような世の中、人と人とが仲良くする、人間の絆、人間同士が助け合う、ということを大切にしたいからです。」
寺本氏のお話を聞き、心に響いた小倉桂子氏 (83)の言葉を思い出した。小倉氏は、私が広島を訪れる数日前にオンラインで行われたブリーフィングで同じテーマについて詳細に語った。
「私が外国にいた時、『おう、お前は日本人だな。日本は酷いことをしたじゃないか』と言って、私に食ってかかった韓国の人がいます。確かにその通りです。でも、一人一人が『あなたの国はこんなことをした』と言って、攻めて言ったら、攻めるよりも私たちは一緒に何かをしなければいけないという方がもっと大切だと思ったのです。」
「私たちは怒りをぶつける相手はアメリカではありませんでした。イギリスではありませんでした。まず、何かというと、初期の時代は私たち自身です。私たちが一番悲しかったのはどうして私は死んで行く人達を助けられなかったかという、そういう罪の思いなんです。次に考えたことは、私たちはこんな悲しい思いをして、この思いをどうしたらいいかということは相手を非難することではなくて、それを乗り越えるためにはまず虚しく死んだ人達の思いを世界に伝えること。こんなことは二度とあってはならないということ。それを伝えるというために全力を尽くしました。」
「勿論、被爆者達は最初にアメリカに対する怒りがあったわけです。けれども、その時アメリカ軍によって言語統制というか、センサーシップがありまして、私たちはできるだけ思っていることを抑えるようにしました。10年のうち、南太平洋で核実験が行われた時、びっくりしました。私たちの経験からすると、もう二度とああいうことは考えられない。核兵器をまだ作るなんて、信じられなかったのです。」
小倉桂子さんによると、原爆が落ちて、最初の10年の間、全然原爆について話さなかったことにもう一つの理由があった。
「被爆者であるということを言いますと、結婚できないと、被爆者であるからということで結婚式がキャンセルになったり、フィアンセが去ったことはあります。小さな8-10歳の子供でしたけれど、原爆の話をしたらお嫁にいけなくなるなんて嫌って、ずっと黙っていました。」
「被爆者であるということを言いますと、結婚できないと、被爆者であるからということで結婚式がキャンセルになったり、フィアンセが去ったことはあります。小さな8-10歳の子供でしたけれど、原爆の話をしたらお嫁にいけなくなるなんて嫌って、ずっと黙っていました。」
「私が外国にいた時、『おう、お前は日本人だな。日本は酷いことをしたじゃないか』と言って、私に食ってかかった韓国の人がいます。確かにその通りです。でも、一人一人が『あなたの国はこんなことをした』と言って、攻めて言ったら、攻めるよりも私たちは一緒に何かをしなければいけないという方がもっと大切だと思ったのです。」
「私たちは怒りをぶつける相手はアメリカではありませんでした。イギリスではありませんでした。まず、何かというと、初期の時代は私たち自身です。私たちが一番悲しかったのはどうして私は死んで行く人達を助けられなかったかという、そういう罪の思いなんです。次に考えたことは、私たちはこんな悲しい思いをして、この思いをどうしたらいいかということは相手を非難することではなくて、それを乗り越えるためにはまず虚しく死んだ人達の思いを世界に伝えること。こんなことは二度とあってはならないということ。それを伝えるというために全力を尽くしました。」
© Sputnik / Eleonora Shumilova
3
被爆体験伝承者の岡本としこ
「平和を捕まえてください」
「平和を捕まえてください」
寺本氏と一緒に被爆体験伝承者の岡本としこ氏も面会に訪れた。岡本氏は広島生まれでも広島育ちでもないが、原爆の記憶を残す活動に貢献するため30年前に東京から広島にやってきた。
「私が最初に広島に来て思ったのは、この広島が経験した原爆というものはどういうものなのかということ。そして被害・影響を受けた被爆者の方達がどういう思いで今まで暮らしてこられたのかということ。それを知りたいと思って、この伝承プログラムに入ったんです。」
“
実際にその勉強を通して何を思ったかといったら、戦争はもう過去のことなのかということです。もうこれから戦争は絶対起こらないのでしょうか。核兵器は使われないのでしょうか。わかりません。でも、私たちは過去から学ぶことができます。それがとても大切なこと。それは私自身だけが学ぶことではなくて、他の方にもわかって欲しいです。それでみんなが過去のことを学び、これからどういう世界にしていきたいか、どうしたら平和を守れるのか。そういうことに私がもし力になれるのならそれは素晴らしいなと思いました。私自身も平和のために自分に何ができるかわかりませんでした。でもこの伝承プログラムを通じて、あぁ、人に話すことができる、わかってもらう努力をすることができる、質問に答えることができると。それが私にできることだったんです。それで伝承者になることを決めました。
写真: AFP/Toru Yamanaka
岡本氏によると、資料館が実施している被爆者の体験を語り継ぐ伝承者を育成するための研修には現在、約40人が参加している。現時点で約150人が被爆体験伝承者として活動しているという。伝承者になるのは簡単なことではない。大きな責任が伴う他、長期にわたる研修を受けなければならない。
»
「伝承プログラムは、被爆体験の伝承を希望している人たちに研修をして、伝承者を育成するというプロジェクトです。それは3年間です。まず、最初の1年は原爆について、広島の歴史について、そして被爆体験というものを勉強します。2年目になると、核被爆者の人、自分が伝えたい被爆体験の人と一緒にミーティングを行います。大体月1回。直接お話をして、いろいろ自分のわからないところ、そういうのを聞いていきます。そのあとは、大体45分のプレゼンテーションを目標とした原稿を書きます。その原稿を書くのは私たちにとって一番大変です。それを寺本さんにチェックしてもらって(彼の伝承者ですから)、今度はプレゼンテーションのテストとなります。それが全部で3回です。それが終わって、大丈夫ですと言われましたら、初めて伝承者としてデビューします。」
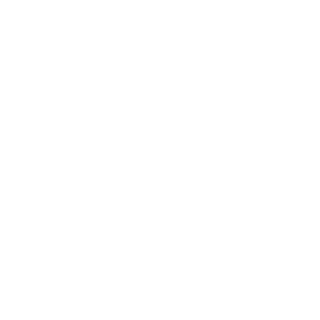
岡本としこ
伝承者
»
なお現在、新型コロナウイルスの影響で伝承プログラム は中断している。しかし岡本氏は、近いうちにも資料館はzoomを使ったミーティングを開始し、オンラインで伝承講話を続けることができると考えている。岡本氏は次のように語っている-
“
「被爆者の方も何人もいらっしゃるのですが、ある方はこう言われています。『いま、みんなは平和の世界に暮らしていますか?平和というのはすぐ逃げていきます。皆さんしっかりと平和を捕まえてください。そしてその平和を大切に持っていてください』と。それは戦前・戦中・戦後を暮らした被爆者の方にしか言えないことです。
また、海外から来られた方は特に『来て初めてわかった』ということを言います。皆さんは本を読んだり、写真を見たりされますけれども、実際にこの資料館に来てわかることもあるんです。それと同じように、この被爆者の方々のお話しを通して学ぶことも大きいです。
だからこそ被爆体験を世代から世代へ繋いでいくということは本当に大切なことです。日本は唯一の被爆国ですけれども、核実験ではそれぞれアメリカでも、オーストラリアでも被爆した人はいます。その事実も踏まえた上で、この日本は被爆によってどういう目にあったのか、それはみんなにわかってもらうことが平和の道につながると私は思いました。」
また、海外から来られた方は特に『来て初めてわかった』ということを言います。皆さんは本を読んだり、写真を見たりされますけれども、実際にこの資料館に来てわかることもあるんです。それと同じように、この被爆者の方々のお話しを通して学ぶことも大きいです。
だからこそ被爆体験を世代から世代へ繋いでいくということは本当に大切なことです。日本は唯一の被爆国ですけれども、核実験ではそれぞれアメリカでも、オーストラリアでも被爆した人はいます。その事実も踏まえた上で、この日本は被爆によってどういう目にあったのか、それはみんなにわかってもらうことが平和の道につながると私は思いました。」
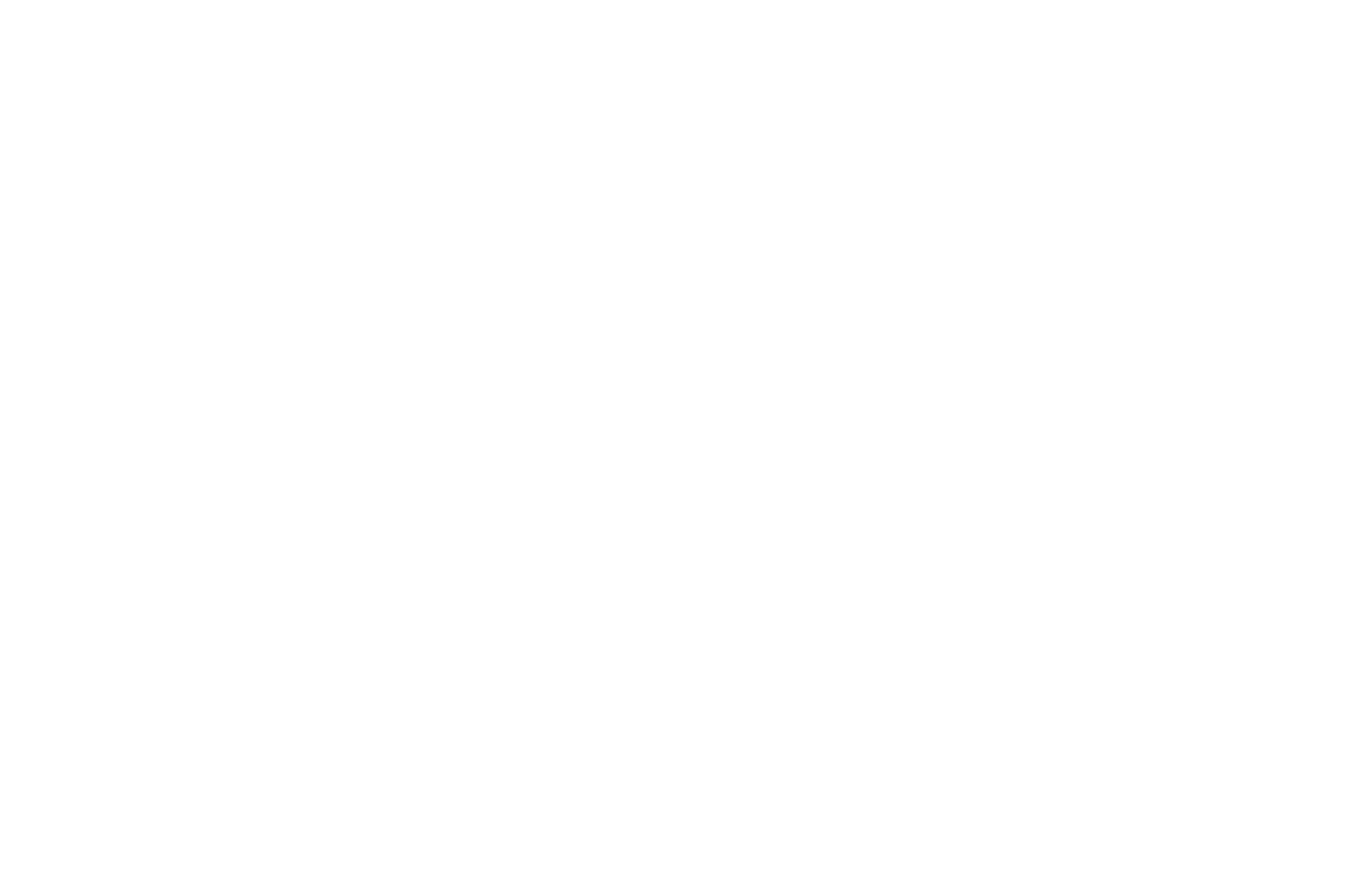
4
ユースピースボランティア:
「広島からは『平和』を
持って帰ることができると思う」
「広島からは『平和』を
持って帰ることができると思う」
広島訪問の最後に私は「ユースピースボランティア」の若い大学生2人にインタビューした。この日はちょうど梅雨明けと重なったため、広島平和記念公園や原爆ドームの近くを歩きながらお話を伺うことができた。
ユースピースボランティアの活動は昨年6月に始まったばかり。だが高校生や大学生の若いボランティアたちは今年2月までに41か国・地域の外国人観光客232人のガイドをした。
彼らが最もよく聞かれる質問の一つは、なぜ広島の若者は平和記念公園を訪れる外国人に対して被爆の実相などを英語で伝えるボランティア活動をするのかというものだという。
ボランティアを務める池田風雅 (広島大学2年生)さんは、ずっと英語ガイドとして自分を試したく、故郷・広島の歴史や現在についてできるだけ多くの人に伝えたいと思っていたという。そして、外国人観光客からの質問は時に非常に難しいこともあるが、外国人観光客と交流することが好きだという。
»
「普通は国際関係に関する質問が多いです。例えば、日本がアメリカの核の傘の下に入っている事実についてなどの質問がよくあります。自分の意見も聞かれます。また、例として、自分は日本が核兵器禁止条約に署名しないことに対してどう思うかと言いますと、日本は原爆が投下された唯一の国として核兵器のない世界に向けて優先・リードしないといけないと感じています。」
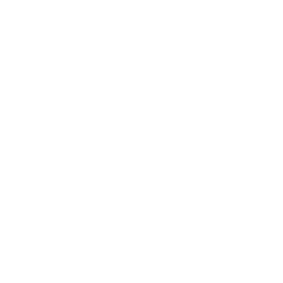
池田風雅
ボランティア
同じくボランティアを務める野村ミカエル介 (広島大学3年生)さんにもお話を伺った。野村さんはフィリピンで育ち、約18年間フィリピンで暮らしていたが、母親が日本人であるため日本の大学に入学した。
»
「ガイドをするのは日本人ではなくて、外国人なので、外国人の立場を知っている自分だからこそ外国人にわかってもらうように伝えることができると思いました。例えば、私たち日本人は被害者だというよりも、全体的に戦争自体はよくないというような感じでガイドをしています。」
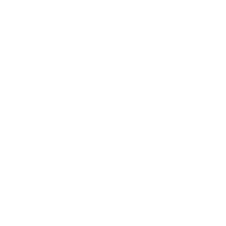
野村ミカエル介
ボランティア
Q:
広島県内および広島県外の日本人は、原爆に関する歴史をどの程度知っていると思いますか?
ボランティア:
人はそれぞれで、興味がある人は知っていますけれど、普通、広島県外では知識として「こういうことが起こった」、歴史にあることは知っていると思いますけれど、今の状況や今の日本の立場などは広島の人はよく知っているんですけれど、県外の人はそこまで知識はないような印象があります。
Q:
ガイド活動中に一番大切にしていることは何ですか?
ボランティア:
ガイドをしている時、私たちは自分たちが話していることではなく、私たちの話を聞いている人たちとどのようにしてつながるかに焦点を当てています。彼らと良い関係を築くため、そして彼らが故郷に帰ったときに、特に歴史的な観点から広島はとても良い場所で、訪れるに値する場所だと話してもらえるようにするためです。
Q:
広島から何を持って帰ることができますか?
野村ミカエル介さん:
広島からは「平和」を持って帰ることができるのではないかと思います。これは戦争の不在や核兵器廃絶についてだけではありません。平和とは単純なものの中にあります。例えば、私たちは異なる文化的背景を持っています。私たちは地球の異なる大陸の出身ですが、私たちにはこのように交流したり、話し合ったり、相互理解を見出そうとする機会があります。そして、私たちがこれを行うことができるという事実は、たとえそれが小さなものだとしても、私たちが「平和」を達成したことをすでに物語っています。これが、あなたが持って帰り、他の人に伝えることができる本当に価値のあるものだと思います。
このアドバイスは、小倉桂子氏の広島についての素晴らしい言葉をふと私に思い出させた。
“
「広島にいらしたら、あの悲惨な原爆当時の話だけではなくて、今の美しい広島を見てください。私たちは復興した広島を見ていただきたいんです。3日後に電車が走ったんですよ。もう食べるものはなかったのに、みんな一生懸命に働きました。5年のうちに、私たちは広島カープという地元の野球チームを作ったんです。私たちはどんなに悲しい時でも、希望があれば立ち上がれます。新しく復興することができるのです。ですから、広島に来て『あぁ、このきれいな街、やればできるもんだな』ということを見ていただきたいです。世界中の皆さん、街を破壊されても、絶対にできると思います。」
Depositphotos / Kuzmire
1945年の原爆投下では、当時およそ35万人だった広島市の人口のうち14万人が犠牲となった。現在、広島市では199万人が暮らしている。

